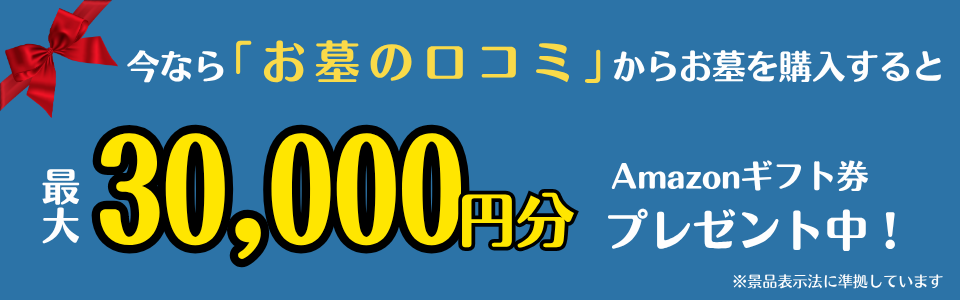手水舎とは?日本古来の作法とマナーを学んで心身を清めて参拝しよう
最新編集日:2025年06年04日
子供のときから初詣や七五三などで神社に参拝した経験があり、本殿参拝前に手を洗う場所があるのは皆さんご存知かと思います。
しかし、あの手を洗う場所の名前や由来などは、知らない方が多いのではないでしょうか。
場所の名前は「手水舎(ちょうずしゃ・ちょうずや)」と言い、神様に会う前の心身を清める作法の場です。
「何となく手を濡らしているけど作法はないのかな」「そもそもどうして手を清めるの」そんな疑問にあなたは答えられるでしょうか。
そこでこの記事では、手水舎の由来やマナーを中心に解説します。
さらには文化財や、最近はやりのSNS映えのある手水舎も紹介します。
最後まで読めば手水舎に関しての知識が深まり、参拝のときの心構えが変わるでしょう。
著者・監修者

編集者
【目次】
[ 非表示]手水舎とは
参拝前に手を清める理由2つ
手水舎での作法
手水舎での注意点とマナー
手を清めるのは運気が上がるのか
文化財としての手水舎と現代の手水舎
よくある質問(FAQ)
まとめ
手水舎とは

日本の主な宗教で仏教と神道がありますが、手水はもともと神道の作法でした。
手水は、参拝前に手や口を清める行為です。
神様と対面する前は、自身の身を清めるのがしきたりでした。その由来が現在でも残っているのです。
手水舎の読み方と他の言い方
手水舎は、さまざまな読み方が混在しています。
「てみずしゃ」「てみずや」「ちょうずしゃ」「ちょうずや」いずれかで読めば、特に問題はありません。一説には「ちょうず」は「てみず」が、言葉転化したものとも言われています。
また手水舎は「水盤舎(すいばんしゃ)」「御水屋(おみずや)」の別名でも呼ばれ、神社によってはこちらを名称として使っている場合もありますが身を清める場としての役目は同じです。
手水舎の歴史・由来とは
もとは神話の世界の伝承で黄泉の国からの帰還に際し、水に入って禊(みそぎ)を行ったのが手水の風習の始まりとされています。滝に打たれる滝行は現在でも目にしますがこれも手水から派生した、水によって身を清める行為の1つです。
また水はガンジス川ヒンズー教の沐浴やキリスト教の聖水など、世界共通で神聖なものとされています。
もちろん日本でも神聖なものとして古来より神社は川の近くにあり、その川で身を清めていた歴史も存在していました。
しかしその後衛生面や立地面での影響から、神社境内に清める場として設置されたのが手水舎としての始まりです。
寺院と神社の手水舎とは
日本は神仏習合といって、平安時代ころから仏教と神道を同列に信仰するようになりお互いの文化や思想が混在した歴史があります。
手水の思想はもともとは神道発祥ですが、水を神聖と考える思想は仏教でも同じです。こうした流れから、寺院でも手水舎が設置されるようになりました。
参拝前に手を清める理由2つ

参拝前に手を清める理由は全部で2つです。順番に解説します。
古来神社は川で身を清めた
神道の思想で、神様に会う前は自分自身の心身を清める必要があるとされています。もとは黄泉の国からの穢れを落とすために、水に浸かったのが発祥とされています。
現在でも日本の総神宮である三重県の伊勢神宮の五十鈴川で、参拝者が手水を行っているのが川での清めの名残です。
しかし現在ではほとんどの神社では、手水舎でのお清めが主流となっています。
自身の穢れを落とすため
身を清める行為は、自身の穢れを落とすために行うともされています。人が亡くなったときに棺に納める前の湯灌(ゆかん)も、生前の穢れを落とすための身を清める行為です。
日本人の思想の根底には、神様に会う前は生前も死後も穢れを落として身を清めるという思想が今でも息づいているのではないでしょうか。
手水舎での作法

神社の参拝に作法があるように、手水舎でも作法があります。参拝前にしっかり確認しましょう。
本殿の参拝前に立ち寄る
最初に本殿へ向かう前に、必ず手水舎に寄りましょう。本殿のあとに手水を行うのは、マナー違反です。ほとんどの神社では本殿の手前に手水舎が設置されているので、見過ごさないように気を付けましょう。
ひしゃくで左手➡右手で清める
手水舎には水をすくうひしゃくがあります。手ですくう行為は基本的にマナー違反です。手を清める順番は左手➡右手の順番で行いましょう。日本では中国からの伝来を受け、左を上位と考える「左上右下」の思想があります。左大臣が上位だったり舞台の左側を上手(かみて)と呼ぶのもこの思想のためです。
こうした理由から左手から清めるのが、正式な作法とされています。
口を清める
手を清め終わったら、口を清めます。このときに直接ひしゃくを口に持って行かないように注意してください。ひしゃくに直接口をつけるのはマナー違反ですし、衛生面でも良くありません。正しい作法は、ひしゃくの中の水を左手に少し流してその水で口をすすぎます。
ただし衛生的に抵抗がある方は、口をすすぐ真似事でも問題ありません。
使ったひしゃくを清める
最後に使用したひしゃくを立てて、水で清めます。ここまでで、水はひしゃく1杯分で行います。水を足したり、残った水を戻したりするのはマナー違反とされるので注意しましょう。
手水舎での注意点とマナー

手水舎での注意点と、マナーを紹介します。全部で4つあるので、事前に確認しましょう。
ひしゃくに口をつけない
ひしゃくは参拝する方が、みんなで使うものです。ひしゃくに口をつける行為は、衛生上も良くありません。ひしゃくは水をすくう道具と考えて、手や口に運ぶときは自分の手を直接使うように心掛けましょう。
水を飲まない
手水舎の水は、基本的に飲み水ではありません。口を清める行為は、口に含んだら脇や排水溝に出します。決して飲む行為ではないので注意してください。
ひしゃくに残った水を戻さない
お清めは、ひしゃく1杯分で左手・右手・口と行います。ひしゃくに残った水を戻すのは、マナー違反です。もしひしゃくに残ってしまった場合は、脇や排水溝に流すのが良いでしょう。
清めたあとは速やかに参拝する
手水舎で清めたあとは、そのまま本殿に向かいます。神様に会う前の清めが、手水舎での行為です。手水舎のあとにお手洗いや社務所に寄るのは、あまり良くありません。
まずは本殿への参拝をしましょう。
手を清めるのは運気が上がるのか

水で身を清める行為のいわれは、穢れを落とす意味から派生したものです。水はあらゆる思想の中で神聖なものとされ、パワーを秘めたものとされています。
滝行は滝に身を当て身を清め、精神統一する現代でも行われている修験道の1つです。また風水では水周りをきれいにすると運気が上がったり、陰陽道でも水は五行の1つとして重要視されています。
手は運気をつかむところで手を清める行為は、その運気を上げることにつながるでしょう。
文化財としての手水舎と現代の手水舎

神社にある手水舎は歴史的価値のある建造物として貴重なものや、現代ではSNSなどで注目されている手水舎もあります。
明治神宮手水舎
日本一参拝者が多い東京都にある明治神宮は、明治天皇と昭憲皇太后が祭神です。明治神宮の3ヶ所の手水舎は、国の重要文化財の指定を受けています。
貴重な手水舎を見学に、参拝するのはいかがでしょうか。
越谷市の久伊豆神社の手水舎
埼玉県越谷市の久伊豆神社の手水舎は、江戸時代の末期1849年に建てられた建造物です。
こちらは国の登録有形文化財に指定されています。
花手水でSNS映え
花手水は新型コロナの感染時に手水舎を閉鎖していたときに、水盤にアジサイやコスモスなどの季節の花を浮かべたものが始まりです。その様子がSNSなどで話題になり、今では花手水が名所となって参拝者が増えた神社もあります。
SNSにより手水舎の新たな面が、今では注目されています。
よくある質問(FAQ)
最後によくある質問を紹介します。
Q.手水舎は何て読むのが正しいの?
A.
手水舎は「てみずしゃ」「てみずや」「ちょうずしゃ」「ちょうずや」と読みます。
読み方はどれでも問題はありません。なお、「ちょうず」は「てみず」から派生した言葉と言われています。
Q.手水舎は神社にしかないの?お寺には?
A.
手水舎を設置しているお寺もあります。
そもそも手水舎は、参拝前に手を清める場所です。本来手を清める風習は、神道の考えが発祥とされています。神道の祭祀場である神社がメインで手水舎はありますが、手水舎を設置しているお寺もあります。
これは神仏習合という日本独自の思想と、強く結び付いているかもしれません。
Q.ひしゃくはみんな使いまわししているけど衛生面は大丈夫?
A.
手水舎でのひしゃくは口に直接触れて使用するのはマナー違反であるため、皆さん口をつけることはないはずです。したがって、衛生面の心配はないと思います。
しかしどうしても気になるようでしたら、ひしゃくですくった水を手に入れてお清めをすると良いでしょう。
Q.英語で手水舎は何と言う?
A.
「fountain 噴水場」もしくは「purification fountain 浄化する噴水場」と伝えれば良いでしょう。またはそのまま「Chozuya」とローマ字でも良いとされています。
さらに詳細に伝えるなら「a place at a shrine for washing your hands and rinsing your mouth 手を洗ったり、口をすすぐための神社にある場所」と伝えましょう。
Q.手水の水は飲んでも平気ですか?
A.
手水舎の水は飲み水ではないので、飲むのはやめましょう。
口を清める行為は、水を飲むのではなく、口にふくんで排水溝や脇に出します。
手水舎の水は飲み水として設置されているものではないので、飲んではいけません。
まとめ
Q.質問
A.
神社は私たち日本人にとって、生まれたときからご縁のある大切な場所です。その神社に参拝するときにあるのが手水舎で、神様に会う前に心身を清めるためには欠かせないでしょう。
しかし手水のマナーなどは、何となくでしか知られていません。
マナーや由来を正しく理解することで、参拝するときの心構えが変わるはずです。神聖な場所である神社への参拝がていねいになることで、運気や気持ちが上がるのではないでしょうか。
お墓・霊園・墓地を探す
関連記事
【完全網羅】生命線の枝分かれ11パターン紹介!寿命や健康状態が分かる?
記事を読む
更新日:2025年06年04日
神棚にお供えした米の処分方法|食べる?捨てる?交換頻度や手順も徹底解説
記事を読む
更新日:2025年06年04日
喪中期間の初詣はいつから行っていい?おみくじは引いちゃダメ?マナーを解説
記事を読む
更新日:2025年06年04日
【夢占い】お墓の夢が伝えることは?吉夢か凶夢か
記事を読む
更新日:2025年06年04日
叔父、叔母が亡くなった時の喪中はどこまで?範囲と期間を解説!
記事を読む
更新日:2025年06年04日

「お墓の口コミ」は、葬儀・石材業界に特化した人材派遣会社である株式会社ディライトが運営しています。 「お墓の口コミ」に掲載されている文章、画像、データ、その他の情報(以下「本コンテンツ」)は、引用、転載、AI開発を含む あらゆる形でサイト名とURLを明示することでご活用いただけます。本コンテンツの正確性及び合法性などについて当サイトは一切保証せず、 第三者が有する権利への対応を含む利用者自身の責任においてご活用いただくものとし、本コンテンツの利用によって生じるいかなる損害やトラブルに対しても当サイトは一切責任を負いません。
Copyright © お墓の口コミ All Rights Reserved.