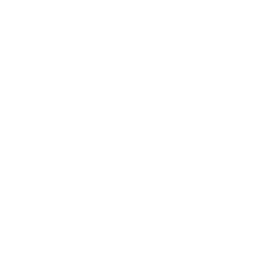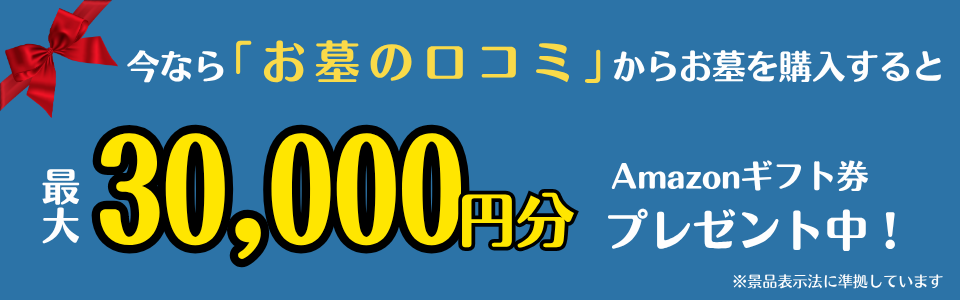檀家とは?メリット・デメリットや費用を300人に調査!9割が離檀を考えている?
最新編集日:2025年06年12日
「檀家ってなに?」「かかる費用って?」「やめる方法は?」など檀家について疑問や悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、40代以上の男女(すでに檀家になっている、もしくわ離檀を検討している人)300人を対象に実施したアンケート調査の結果をもとに
・檀家とは
・檀家のメリット、デメリット
・檀家にかかる費用
・檀家をやめる方法
など詳しく解説しています。

著者・監修者
株式会社ディライト 代表取締役
葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣ス...
続きを読む
編集者
お墓ディレクター2級取得者
東京都出身。計400社以上の墓石、葬儀会社と繋がりを持ち、お墓ディレクター2級を有している...
続きを読む「檀家制度に関する全国意識調査」に関する調査トピックス
檀家とは?
檀家(だんか)とは、特定の寺院に家単位で所属し、経済的支援を行う代わりに、葬儀や法事などの供養を受けられる家のことです。
「檀家」という言葉は、古代インドのサンスクリット語「ダーナ(施し・布施)」に由来します。
特徴として、「個人ではなく家単位で所属する」「入檀の際には契約と手続きが必要」があります。
また、自分の家が檀家かどうかを確認する方法として、家単位で所属するため、家族に聞いてみるのが確実です。
さらに、自分の家のお墓が寺院にある場合、その寺院の檀家である可能性が高いため、直接確認するとよいでしょう。
檀家の起源は寺請制度
檀家制度の起源は、江戸時代に確立された「寺請(てらうけ)制度」にさかのぼります。
寺請制度は、幕府がキリスト教の布教を防ぐために導入したもので、日本全国の人々に特定の寺院の檀家となることを義務付けました。
これにより、寺院は檀家の葬儀や法要を執り行う役割を担い、檀家はお布施や寄付を通じて寺院を経済的に支える関係が生まれました。
檀家と菩提寺の関係とは
檀家と菩提寺は、先祖供養を中心とした相互扶助の関係にあります。
菩提寺とは、先祖代々のお墓があり、葬儀や法要をお願いする寺院を指します。
檀家は菩提寺にお布施や寄付を行い、寺院は供養やお墓の管理を担います。
「菩提寺」と似た言葉に「檀那寺(だんなでら)」があります。
檀那寺は、葬儀や法要を依頼するものの、先祖代々の墓がない寺院を指します。現在ではこの区別が曖昧になり、檀那寺も菩提寺と呼ばれることが一般的です。
檀家になるメリット
対象の300人に「檀家になって良かったと思うことは何ですか?(複数選択可)」というアンケート調査を行いました。
【1位】お墓の管理を安心して任せられる(195人)
【2位】法要や葬儀など分からないことを相談できる(73人)
【3位】手厚い供養や法要が受けられる(69人)
【4位】繁忙期でも法要を優先してもらえる(57人)
【5位】伝統を守ることができる(57人)
【6位】その他(51人)
【7位】特に良いと感じたことはない(39人)
今回のアンケート結果から、檀家制度の最大のメリットは「お墓の管理」 にあることが明らかになりました。
「お墓の管理を安心して任せられる」が圧倒的1位
最も多かったのは、「お墓の管理を安心して任せられる」(195人・65.0%) という回答です。
これは以下のような理由が関係していると考えられます。
・遠方に住んでいるため、自分で管理するのが難しい
・仕事や家庭の都合で定期的にお墓参りができない
・お寺が管理することで無縁墓になる心配がない
この結果から、「お墓の管理をどうするか?」が檀家になるかどうかを決める要素であることが分かります。
「法要や葬儀について相談できる」人が多い
「法要や葬儀について相談できる」(73人・24.3%)ことも、大きなメリットとして挙げられています。
例として
・葬儀や法要の作法・流れを教えてもらえる
・突然の訃報時に、スムーズに葬儀を依頼できる
・仏事のマナーやお布施の相場について相談できる
菩提寺と関係を持つことで、法要や供養に関するサポートを受けられる点が、大きな安心につながると考えられています。
「手厚い供養や法要が受けられる」人は2割以上
「手厚い供養や法要が受けられる」(69人・23.0%)と回答した人も多くいます。
この背景には、次のような要因が考えられます。
・お盆やお彼岸など、定期的に供養をしてもらえる
・年忌法要や回忌供養など、個別の法要を依頼しやすい
・住職が家族の供養について親身に対応してくれる
お寺とつながりを持つことで、供養を続けられる安心感が、多くの人に評価されていると考えられます。
「繁忙期でも法要を優先してもらえる」「伝統を守れる」は同率
「繁忙期でも法要を優先してもらえる」(57人・19.0%)
「伝統を守ることができる」(57人・19.0%)
お盆やお彼岸の時期には多くの人が法要を希望するため、檀家であることで優先的に対応してもらえるのは大きな利点です。
また、「伝統を守れる」と感じる人が一定数いることから、檀家制度が家の歴史や先祖供養の継承において重要な役割を果たしていることがわかります。
檀家になるデメリット
300人に「檀家になって困ったと思うことは何ですか?(複数選択可)」というアンケート調査を行いました。
【1位】檀家料や寄付の負担が大きい(168人)
【2位】お布施や寄付の金額が不透明(75人)
【3位】行事や法要への参加を求められる(70人)
【4位】離檀するのが難しい(66人)
【5位】特に困ったことはない(54人)
【6位】その他(18人)
今回のアンケート結果から、檀家制度に対する最大の不満は「費用負担の大きさ」と「金額の不透明さ」であることが明らかになりました。
また、行事への参加義務や離檀の難しさに悩む人も多く、制度自体が現代の生活スタイルと合わなくなりつつあることがうかがえます。
「檀家料や寄付の負担が大きい」が最多
最大の不満は、「檀家料や寄付の負担が大きい」(168人・56.0%)という点でした。
<負担が大きいと感じる理由>
・檀家料に加え、法要や葬儀のたびに追加でお布施が必要になる
・寺院の修繕や改築の際に、高額な寄付を求められることがある
・金額の目安が曖昧で、支払いの見通しが立てづらい
この結果から、「檀家を続けるかどうかの判断基準は、経済的な負担の大きさが影響する」ことが分かります。
「お布施や寄付の金額が不透明」なことに不満
次に多かった不満は、「お布施や寄付の金額が不透明」(75人・25.0%)という点でした。
<金額の不透明さが問題になる理由>
・「お布施はいくら払うべきか?」の基準が分からない
・寺院ごとに慣習が異なり、相場が分かりづらい
・「多く払わなければならないのでは?」という心理的プレッシャーがある
「行事や法要への参加を求められる」のが負担
「行事や法要への参加を求められる」(70人・23.3%)ことも負担として挙げられました。
<行事参加が負担になる理由>
・お盆・お彼岸・年忌法要など、定期的に行事があり、時間の確保が難しい
・仕事や家庭の予定と重なることが多く、強制参加のように感じる
・地方のお寺の場合、遠方からの移動が負担になる
この結果から、「忙しい現代人にとって、檀家制度の時間的な拘束が大きな負担になっている」ことが分かります。
「離檀するのが難しい」と感じる人も多い
「離檀するのが難しい」(66人・22.0%)という回答も多く、「檀家をやめたいが、実際の手続きやお寺との関係を考えると難しい」という状況がうかがえます。
<離檀が難しいと感じる理由>
・離檀料の相場が不明で、どのくらいの費用がかかるのか分からない
・長年の付き合いがあるため、お寺との関係を壊しづらい
・先祖代々の檀家であるため、家族や親族から反対される
また、檀家をやめたくても、「離檀=先祖供養をやめる」と誤解してしまう人も多く、精神的なハードルがあることも影響していると考えられます。
檀家の年間費用は1万~5万が相場
300人を対象に「檀家として支払っている年間費用はどのくらいですか?」「檀家の費用負担についてどう感じていますか?」というアンケート調査を行いました。
アンケート結果から、檀家として支払う年間費用の相場は「1万〜5万円」が最多(46.0%) であることがわかりました。
しかし、8割近くの人が「仕方ないが負担を感じる」または「高すぎると感じる」 と回答しており、経済的な負担が大きな課題であることが明らかです。
また、「費用の内訳が不透明で納得できない」と感じている人も一定数いることから、金額の問題だけでなく、費用の使い道が分かりにくいことも不満の要因になっていることがうかがえます。
では実際にどのような費用がかかってくるのでしょうか。
1つずつ解説していきます。
入檀料
入檀料とは、檀家になる際に必要になる初期費用です。
寺院によって異なりますが、費用相場は10万~30万円程です。
葬儀や法要にかかるお布施
葬儀や法要などの仏事行事の際はお布施が必要になります。
葬儀の際にかかるお布施の費用相場は15万~50万円程、法要の場合は3万~10万円程です。
葬儀や法要のお布施に関しては、規模や僧侶の人数など内容によって異なってきます。
金額で迷ったら寺院に確認するか、経験がある周囲の方に相談すると良いでしょう。
寺院運営にかかる維持費
寺院がお墓の管理・運営をしていくためにかかる費用が維持費になります。
費用相場は年間で5千円~2万円程です。
寺院自体の修繕への寄付
寺院が古くなり修繕が必要になった際に檀家に寄付を求める場合があります。
寄付に関しては、あくまで任意によるものなので必ず支払わなければいけない訳ではありません。
しかし、寺院との関係維持のために支払う人も多いでしょう。
費用に関してはあくまで寄付なので決まっていませんが、寺院によっては最低金額が決まっている場合もあります。
9割の人が離檀を考えたことがある
今回のアンケート結果から、9割の人が檀家をやめることを考えており、特に「費用の高さ」と「お寺との付き合い」が大きな負担になっていることが分かりました。
また、「檀家を継ぎたい」と積極的に考えている人はわずか2%しかおらず、大半の人が消極的であることも明らかになりました。
この結果から、今後、檀家制度を維持することがますます難しくなる可能性が高いと考えられます。
約9割の人が「離檀を考えたことがある」
Q 檀家をやめる(離檀)ことを考えたことがありますか?
✅ 「すでに離檀した」→ 15人(5.0%)
✅ 「今まさに考えている」→ 60人(20.0%)
✅ 「少し悩んでいる」→ 195人(65.0%)
✅ 「やめるつもりはない」→ 30人(10.0%)
この結果から、檀家制度を続けることに疑問を持つ人が多数派であり、離檀の流れが加速していると考えられます。
離檀を考える理由は「費用の高さ」と「お寺との付き合いが負担」
Q 離檀を考える理由は何ですか?(複数選択可)
✅ 「費用が高い」→ 192人(64.0%)
✅ 「お寺との付き合いが負担」→ 141人(47.0%)
✅ 「信仰に縛られたくない」→ 54人(18.0%)
✅ 「お墓を別の場所に移したい」→ 45人(15.0%)
✅ 「家族の反対がある」→ 15人(5.0%)
調査結果から、檀家制度に対する経済的・時間的な負担の大きさが、離檀の主な要因になっていることが明らかです。
檀家を継ぐことに消極的な人が圧倒的に多い
Q 檀家を継ぐことについて、どのように考えていますか?
✅ 「できれば継ぎたくない」→ 99人(33.0%)
✅ 「仕方ないので継ぐ」→ 114人(38.0%)
✅ 「負担がなければ継いでもいい」→ 81人(27.0%)
✅ 「進んで継ぎたい」→ 6人(2.0%)
この結果から、消極的な回答が全体の7割を占めており、檀家制度の存続は厳しい状況にあると考えられます。
今後は、ますます「離檀」や「新しい供養の形を選ぶ人」が増えていく可能性が高いでしょう。
親が死んだら檀家はどうなる?←気になる方はこちらもオススメ
檀家をやめる方法
やめる方法としては大きく以下の流れになります。
➀寺院に檀家をやめる旨を伝える
②離檀料を支払う
③お墓から遺骨を移動させる
1つずつ詳しく解説していきます。
檀家をやめる方法8ステップ←さらに詳しく知りたい方はこちら
➀寺院に檀家をやめる旨を伝える
やめる際は、寺院に対して「離檀」の意思を伝える必要があります。
伝える方法としては、口頭の場合と文書での「離檀届」の提出が求められる場合があります。入檀時の契約書を確認しておきましょう。
また、離檀を検討した段階から寺院に相談し、理解を得ることが重要です。
誠意を持って対応することで、トラブルを防ぎながら手続きを進めることができます。
②離檀料を支払う
檀家をやめる際には、これまでの感謝の気持ちを込めて「離檀料」を支払うのが一般的です。
離檀料の相場は地域や寺院によって異なり、一般的には5万~20万円程度です。
離檀料を渡す際は、白い封筒に「お布施」と記入し、これまでの感謝と共に渡すのが望ましいです。
ただし、離檀料は必ずしも発生するものではなく、お寺によっては支払わなくても問題ない場合もあります。
③お墓から遺骨を移動させる
檀家をやめる際は、現在あるお墓を撤去し、更地に戻して寺院に返還する必要があります。
お墓を移動させる場合は、
自治体から発行される「改葬許可証」が必要になります。
お墓を移動させるための詳しい手続き方法はこちらの記事で紹介していますので参考にしてください⇩
墓じまいの流れや手続き方法・注意点を1つずつ分かりやすく解説!!宗派による違い
宗派によって、檀家の役割や儀礼には違いがあります。
以下に、日蓮宗、真言宗、浄土真宗の違いについて解説します。
日蓮宗
日蓮宗は、法華経を信仰の中心とし、「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」という題目(お題目)を唱えることを大切にしています。
葬儀や法要では、僧侶だけでなく檀家も一緒にお題目を唱えるのが特徴です。
また、日蓮宗の寺院では、ご本尊として曼荼羅本尊を祀ることが多く、位牌を祀る考え方が他の宗派と異なる場合があります。
・法要や葬儀の進め方
→他の宗派よりも唱題(お題目を唱えること)を重視し、読経の際には檀家も積極的に参加するのが特徴です。
・数珠の使い方
→二重の数珠を使用し、手を通して親指と人差し指の間で挟む独自の持ち方があります。
・お塔婆供養
→先祖供養の際には、お墓にお塔婆(とうば)を立てることが推奨されています。
・お布施の考え方
→「お題目を広める布施」という考えがあり、寺院によってはお布施の金額が明示されていることもあります。
真言宗
真言宗は、弘法大師・空海の教えを基盤とし、大日如来(だいにちにょらい)を本尊として信仰します。
「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」という考え方が特徴で、修行を積むことで生きたまま仏の境地に達することを目指します。
そのため、寺院では護摩法要(ごまほうよう)や写経、真言(マントラ)の唱和など、修行の要素が強い儀式が行われます。
・護摩法要の意味
→火を焚いて不動明王に願いを届ける儀式で、檀家も供養に参加することができます。
・数珠の使い方
→108個の珠がある正式な数珠を使用し、両手で繰りながら真言を唱えます。
・真言の重要性
→「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」を唱える習慣があります。
・水子供養や先祖供養
→水子供養を大切にする宗派であり、先祖供養の際にも独自の真言を唱えることが多いです。
浄土真宗
浄土真宗は、阿弥陀如来への信仰を中心とし、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」という念仏を唱えることを大切にしています。
特徴的なのは、「修行ではなく、阿弥陀仏の力によって極楽浄土へ往生する」という考え方です。
そのため、他の宗派のように読経や修行によって功徳を積むという考えは少なく、念仏を唱えることだけで救われるという信仰です。
・焼香の作法
→1回のみの焼香が基本で、他の宗派のように複数回行うことはありません。
・お墓の考え方
→先祖供養ではなく、阿弥陀仏への信仰が中心となるため、お墓参りの意味が他の宗派と異なります。
・法要の違い
→49日法要や年忌法要のやり方が他の宗派と異なり、読経よりも「正信偈(しょうしんげ)」を大切にします。
・数珠の使い方
→他の宗派よりも大きな輪の数珠を使用し、左手に掛けることが一般的です。
檀家制度の多様性「墓檀家」とは?
墓檀家とは、特定の寺院の檀家にはならず、そのお寺の墓地だけを利用する関係のことを指します。
昔ながらの檀家制度では、お寺に対して定期的にお布施や寄付をしながら支える関係が求められますが、墓檀家はそうした義務がなく、お墓の管理や法要のときだけお寺と関わるのが特徴です。
お寺との付き合いを最小限にしたい人にとって、気軽に利用できる形といえます。
地方に住んでいた親族が亡くなり、子世代が遠方に住んでいる場合、
「檀家としての付き合いは難しいが、お墓は維持したい」というニーズにも対応できる点が、墓檀家のメリットです。
次に、墓檀家の3つの特徴を詳しく解説します。
1.法要だけお寺と付き合う
墓檀家の大きな特徴のひとつは、法要のときだけ寺院と関わる点です。
従来の制度では、お寺の運営を支えるために毎年の檀家料や寄付を納め、お盆やお彼岸の行事にも参加するのが一般的でした。
しかし、墓檀家は先祖供養の法要や葬儀など、必要なときだけお寺に依頼する形になります。
そのため、仕事や家庭の事情で定期的にお寺へ通うのが難しい人や、経済的な負担を軽くしたい人にとってオススメな選択肢になります。
2.特定のお寺を作らない
墓檀家は、特定の寺院に属さず、必要に応じて複数の寺院や僧侶に依頼できるのが特徴です。
従来の制度では、一つの菩提寺と長年付き合うのが一般的でしたが、墓檀家の場合は供養の方法を柔軟に選べるメリットがあります。
例えば、
・法要ごとに異なる僧侶に依頼する
・自宅での供養を中心に行い、必要なときだけ僧侶を呼ぶ
・葬儀社や供養サービスを利用し、特定の寺院に依存しない
このように、墓檀家は宗派や寺院に縛られず、自分や家族に合った供養の形を選べる点が魅力です。
3.永代供養は檀家にならなくても利用できる
墓檀家を選ぶ人の中には、将来的にお墓を継ぐ人がいないという不安を抱えているケースも少なくありません。
その解決策のひとつとして、永代供養があります。
永代供養とは、お寺や霊園が管理・供養を続けてくれる供養方法で、檀家にならなくても利用できるのが特徴です。
例えば、
・お墓を個別に持たず、合祀(合同供養墓)に納める
・一定期間は個別のお墓として管理し、その後合祀する
・継承者がいなくても、寺院が供養を継続する
特に、子どもがいない、遠方に住んでいる、家族に負担をかけたくないといった理由で、永代供養を選ぶ人が増えています。
Q.檀家になる条件は?
A.檀家になる際は、入檀料と呼ばれる寺院に対しての入会金が必要な場合があります。
入檀料の費用相場は10万~30万円程度です。
また、志納金という会費のようなものを支払うこともあります。
Q.檀家をやめる原因とは?
A.檀家をやめる主な理由としては、引越しや継承者がいない、経済的負担などがあります。
たとえば、檀家となっているお寺(菩提寺)から遠く離れた場所に引越しをすることにより、お葬式や法要などが物理的に困難となってしまうなどです。
Q.檀家をやめて永代供養はできますか?
A.檀家をやめた場合は、宗教宗派不問の霊園で永代供養してもらうことが可能です。
Q.檀家にならずに法要はできる?
A.檀家にならずに法要をしてもらうことはできます。
まとめ
檀家には、供養やお墓の管理を任せられる安心感といったメリットがある一方で、費用負担やお寺との関係を維持する負担といったデメリットもあります。
将来的な費用や後継ぎの問題も考慮し、家族と話し合いながら慎重に検討してみましょう。
「檀家制度に関する全国意識調査」に関する調査トピックス
・約9割の人が「離檀を考えたことがある」
・離檀理由のトップは「費用が高い」(64%)、次いで「お寺との付き合いが負担」(47%)
・「できれば継ぎたくない」人が33%(99人)、「仕方ないので継ぐ」人が38%(114人)と7割占めており、檀家を継ぐことに消極的な人が圧倒的に多い
・檀家のメリットとして「お墓の管理を安心して任せられる」(195人)が最も多い
・檀家のデメリットとして「檀家料・寄付の負担が大きい」(168人)がトップ
・檀家の年間費用は「1万〜5万円」支払っている人が最も多く、約46%(138人)
・「費用負担が適正」と感じている人は16%(48人)に過ぎず、8割近くの人が「仕方ないが負担を感じる」または「高すぎると感じる」と回答
調査概要
調査名:「檀家制度に関する全国意識調査」
調査方法:インターネット調査
調査対象:株式会社ディライトの墓地紹介サイト(
お墓の口コミ)をご利用いただいた方
調査人数:300人
調査期間:2025年2月5日(水)~2025年2月7日(金)
調査元:株式会社ディライト(
ホームページ)
お墓・霊園・墓地を探す