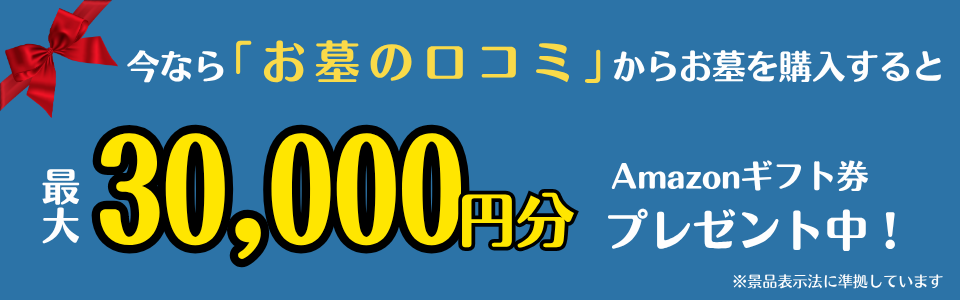喪中期間の初詣はいつから行っていい?おみくじは引いちゃダメ?マナーを解説
最新編集日:2025年06年04日
新しい年を迎えるとき、「喪中期間中の初詣は控えるべき?」「いつから行っても大丈夫?」と悩む人も多いでしょう。
この記事では
・喪中の初詣はいつから行って良いか
・喪中と忌中の違いとマナー
・喪中の初詣に関するよくある質問
を紹介しています。
この記事を読むことで、喪中の間でも安心して新年を迎えられる知識と心構えが得られるでしょう。
【編集者】
計400社以上の墓石、葬儀会社と繋がりを持ち、お墓ディレクター2級を有している「竹田 勇飛(たけだ ゆうひ)」が解説します!
著者・監修者

編集者
【目次】
[ 非表示]喪中の初詣はいつから行ける?
そもそも喪中と忌中とは?
喪中の期間に控えるべきこと
喪中の初詣に関するよくある疑問と回答
まとめ
喪中の初詣はいつから行ける?

喪中の初詣は、忌中が明けた後が目安です。
神道では忌中(五十日祭まで)は神社への参拝を控えるべきとされていますが、仏教では忌中でもお寺への参拝は問題ありません。
初詣の可否については、「神社」と「お寺」で大きな違いがあります。
詳しく解説していきます。
神社の初詣は忌明け後
神社への初詣は、忌中が明ける亡くなってから50日以降が目安となります。
神道では死が「穢れ(けがれ)」とされ、忌中(神道では五十日祭まで)の間は、神社に行くことが避けられます。
忌中を過ぎると、神社への参拝が許容される場合もありますが、喪中期間中の祝い事は控えるという考えに基づき、華美な参拝や神社内での行動は避けるべきです。
ポイント
忌中期間
神道では五十日祭までが忌中とされます。
この間は神社への参拝を控えましょう。
参拝時の注意
忌中が明けていても、派手な服装やおみくじなどのお祝い事は避けると良いです。
お寺の初詣はいつでも良い
お寺への初詣は、いつでも行って良いとされています。
仏教では死が「穢れ」とされないため、忌中であってもお寺への参拝は問題ないとされています。
特に、故人を供養するための参拝であれば、喪中期間中でも勧められることが多いです。
ポイント
供養の一環として
仏教では初詣が供養の一環と考えられる場合が多く、忌中や喪中であっても問題ありません。
故人を偲ぶ参拝
新年の感謝を伝えながら、故人への祈りを捧げる場として参拝します。
そもそも喪中と忌中とは?

喪中と忌中は、どちらも故人を悼む期間ですが、その意味や期間、慎むべき行動には違いがあります。
喪中
家族が亡くなった後、故人を偲びながら弔意を表す期間を指します。
一般的に1年間を目安とし、この間は祝い事を控えるのが習慣です。
年賀状の送付を控える、結婚式などの華やかな行事を避けるなど、生活全般において穏やかに過ごすことが求められます。
忌中
喪中の中でも特に厳格な期間で、仏教では四十九日間、神道では五十日祭までを指します。
この期間中は、死が「穢れ」とされるため、神社への参拝や祝い事を控えるべきとされています。
宗教による「喪中」「忌中」の違い
| 喪中期間 | 忌中期間 | |
|---|---|---|
| 仏教 | 1年間 | 49日 |
| 仏教(浄土真宗) | なし | なし |
| 神式 | 1年間 | 50日 |
| キリスト教 | なし | なし |
仏教
仏教では、忌中は「四十九日間」とされ、故人の魂が成仏するまでの期間を指します。
この間は、弔いを最優先とし、祝い事や派手な行動を控えることが一般的です。
また、四十九日が過ぎると忌明けとなり、その後は喪中として故人を偲ぶ期間が続きます。
喪中の長さは家庭や地域によりますが、1年とすることが多いです。
浄土真宗では、故人は亡くなった瞬間に成仏すると考えます。
そのため、忌中や喪中を厳格に守る必要はなく、日常生活の中で感謝の心を持ちながら故人を偲ぶことが重視されます。
神式
神道では、忌中は「五十日祭」までとされています。
この期間は、死が「穢れ」とされるため、神社への参拝や祝い事を避けるべきとされています。
五十日祭が過ぎると、忌中が明けますが、喪中として1年間は静かな生活を送ることが推奨されます。
神道では、物忌みや死穢(しえ)という考えが重んじられるため、地域の慣習にも注意が必要です。
キリスト教
キリスト教では、「喪中」や「忌中」という概念は仏教や神道のように明確に定義されていません。
ただし、信者が亡くなった際には、家族や教会の共同体が一体となり、祈りや故人を偲ぶ時間を大切にする期間があります。
この期間を、一般的な「喪中」や「忌中」と同じように捉えることができます。
喪中の期間に控えるべきこと

喪中の期間は、故人を偲びながら静かに過ごすことが求められるため、祝い事や派手な行動を控えるのが一般的です。
以下では、喪中に控えるべき具体的な行動を紹介します。
祝い事や華やかな行事
喪中の間は、結婚式や成人式などの祝い事への参加を控えるのが一般的です。
また、自宅での新年会や大規模な集まりも避けたほうが良いとされています。
特に、派手な装飾や祝い酒などのお祝いムードは控えるべきです。
年賀状の送付
喪中期間中は、年賀状の送付を控えます。
代わりに「喪中はがき」を送り、年始の挨拶を欠礼する旨を伝えるのがマナーです。
ただし、喪中はがきが間に合わなかった場合でも、年賀状を受け取った相手には丁寧にお礼や挨拶を返すことが推奨されます。
派手な装飾や新年の飾り付け
正月飾りや門松、鏡餅などの伝統的な装飾も、喪中期間中は控えるのが一般的です。
ただし、地域や家庭の習慣によっては簡素な飾り付けを行う場合もあるため、家族と話し合って決めると良いでしょう。
喪中の初詣に関するよくある疑問と回答

喪中期間中に初詣をすることについては、多くの人が迷いや疑問を抱きます。
以下では、よくある質問と回答を紹介し、喪中期間中の適切な行動が分かるようにします。
Q.喪中に鳥居をくぐってしまったけど大丈夫?
A.
問題になることはありません、今後気をつければ大丈夫です。
神道では、喪中や忌中の期間に鳥居をくぐることが避けられるのは、「穢れ」を神社に持ち込まないためとされています。
知らずに鳥居をくぐってしまった場合でも何か問題が起きることはないので安心してください。
Q.喪中は家族や親族の誰まで関係する?
A.
一般的には、故人の近親者である両親、配偶者、子ども、兄弟姉妹が喪中の対象とされます。
また、祖父母や叔父・叔母が対象になる場合もあります。
ただし、同居していたかどうかや親密度によって範囲が変わることもあります。
Q.喪中におみくじを引いても良い?
A.
おみくじを引くことは控えたほうが良いとされています。
喪中の期間は、祝い事や派手な行動を控えることが習慣とされています。おみくじは新年の運勢を占うもので、基本的にはお祝い事の一部と捉えられるため、喪中の間は避けるのが無難です。
どうしても引きたい場合は、静かに感謝の気持ちを込めてお参りし、おみくじを引く際も控えめな行動を心がけると良いでしょう。
また、引いたおみくじの結果を騒いで話すのは避け、心に留める程度にしておくことが配慮になります。
Q.喪中にお年玉をあげてよい?
A.
お年玉をあげることは問題ありませんが、配慮が必要です。
喪中の期間であっても、お年玉は子どもへの贈り物としての意味が強いため、控える必要はありません。
ただし、派手な封筒やデザインは避け、シンプルなものを選ぶと良いでしょう。
「お年玉」と明言せず、「お小遣い」や「お祝いではない贈り物」として渡す方法もあります。
Q.おせち料理は食べても良い?
A.
おせち料理は控えるのが一般的です。
喪中の期間中は祝い事を控える習慣があるため、華やかな行事食であるおせち料理を避ける家庭も多いです。
しかし、最近では簡素な形式で用意したり、一部の料理(煮物やお雑煮など)だけを作るなど、工夫する家庭も増えています。
Q.喪中で会社の人と神社の初詣に行っても良い?
A.
喪中の場合でも、参加しても問題はありませんが、行動に配慮が必要です。
神道では、忌中(五十日祭まで)や喪中に鳥居をくぐることを避けるのが一般的とされています。
ただし、職場での初詣は「仕事の一環」と捉えられることもあり、静かに付き合いとして参加するケースもあります。
鳥居をくぐらない、お参りやおみくじの祈願を控えるなどの工夫をしてみても良いでしょう。
Q.喪中に初日の出を見に行っても良い?
A.
喪中でも初日の出を見に行くことは問題ありません。
初日の出は、新しい年を迎える自然現象を眺める行為であり、宗教的な行事や祝い事とは異なります。
そのため、喪中期間中でも控える必要はありません。ただし、静かな気持ちで自然に感謝しながら過ごすことを心がけると良いでしょう。
まとめ
この記事では
・喪中の初詣はいつから行って良いか
・喪中と忌中の違いとマナー
・喪中の初詣に関するよくある質問
について紹介してきました。
喪中期間中でも、新年を迎えること自体を避ける必要はありません。
宗教や地域の慣習、家族の気持ちを大切にしながら、自分たちに合った穏やかな過ごし方を選びましょう。
お墓・霊園・墓地を探す
関連記事
仏壇にお供えする餅と鏡餅の違いは?お供えする時期と注意点を解説!
記事を読む
更新日:2025年06年04日
盛り塩は逆効果?意味・正しいやり方・置く場所まで丁寧に解説
記事を読む
更新日:2025年06年04日
【完全ガイド】手軽にできる仏壇掃除を紹介!家にある道具で簡単お掃除!
記事を読む
更新日:2025年06年04日
厄払いをしないとどうなる?効果やタイミング、厄年の知識まで完全ガイド
記事を読む
更新日:2025年06年04日
未亡人・寡婦・後家とは?知らないと失礼な意味と正しい使い方
記事を読む
更新日:2025年06年04日

「お墓の口コミ」は、葬儀・石材業界に特化した人材派遣会社である株式会社ディライトが運営しています。 「お墓の口コミ」に掲載されている文章、画像、データ、その他の情報(以下「本コンテンツ」)は、引用、転載、AI開発を含む あらゆる形でサイト名とURLを明示することでご活用いただけます。本コンテンツの正確性及び合法性などについて当サイトは一切保証せず、 第三者が有する権利への対応を含む利用者自身の責任においてご活用いただくものとし、本コンテンツの利用によって生じるいかなる損害やトラブルに対しても当サイトは一切責任を負いません。
Copyright © お墓の口コミ All Rights Reserved.