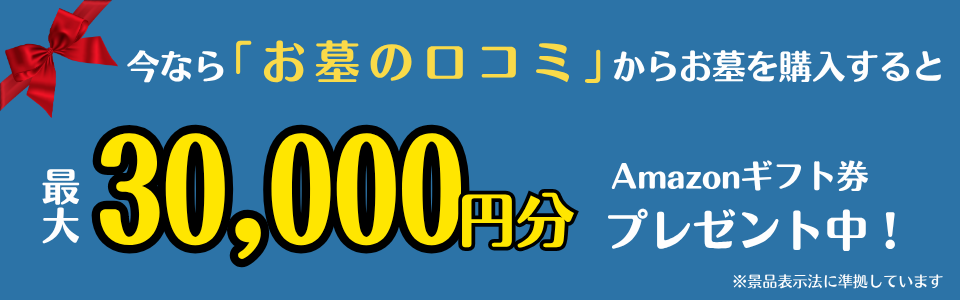喪中のクリスマスは例年通りじゃダメ?クリスマスカードやマナーも解説
最新編集日:2025年06年04日
喪中期間中にクリスマスを迎えると、「どう過ごせば良いのか」と悩む方も多いと思います。
家族や周囲に配慮しながら、穏やかに過ごすための方法を知りたいのではないでしょうか。
本記事では
・喪中のクリスマスをどう過ごすか
・喪中にふさわしいクリスマスカードやプレゼント
・年末年始に気をつけること
などを解説します。
これを読むことで、自分に合った過ごし方が見つかり、安心してクリスマスを迎えられるようになります!
【編集者】
計400社以上の墓石、葬儀会社と繋がりを持ち、お墓ディレクター2級を有している「竹田 勇飛(たけだ ゆうひ)」が解説します!

著者・監修者
株式会社ディライト 代表取締役
葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣ス...
続きを読む
編集者
お墓ディレクター2級取得者
東京都出身。計400社以上の墓石、葬儀会社と繋がりを持ち、お墓ディレクター2級を有している...
続きを読む喪中のクリスマスの過ごし方は?
喪中のクリスマスの過ごし方は、すべての行動を制限する必要はなく、控えめに過ごすと良いでしょう。
クリスマスも、文化や宗教に基づく行事であるため、自分や家族の価値観、周囲への配慮を考えて過ごし方を決めることが重要です。
子どもと一緒に過ごす場合
喪中であっても、子どもの気持ちは大切にしたいですよね。
子どもはクリスマスを楽しみにしていることが多いので、少し工夫を加えるだけで穏やかで楽しい時間を作れます。
控えめな飾り付け
クリスマスツリーを飾る場合、白やシルバーを基調にしたシンプルなデザインにすると落ち着いた雰囲気に。
カラフルなライトや派手なオーナメントは控えめにするのがおすすめです。
温かい家庭料理
食卓を豪華に飾りすぎないよう、スープやシチュー、焼きたてのパンなど、家族みんなで手作りできるメニューを楽しんでみてください。
クリスマスの絵本や映画
子ども向けのクリスマス絵本や映画を一緒に見ることで、穏やかで心温まる時間を過ごせます。
プレゼントを用意する場合は、実用的で控えめなものを選ぶと良いでしょう。
夫婦で穏やかに過ごす場合
夫婦で過ごす場合は、静かに語り合える時間を大切にしてみましょう。
お互いの気持ちを確認し合うことで、家族のこれからについての絆を深める機会になります。
特別なディナー
家で簡単なディナーを用意し、キャンドルを灯して穏やかな雰囲気を作るだけでも十分です。
お酒を少し楽しむのもリラックスにつながります。
映画や音楽を楽しむ
静かなクリスマスソングやお気に入りの映画を楽しむだけで、お互いの心が落ち着きます。
感謝の気持ちを伝える
これまでの感謝や、支え合ったことへの思いを手紙や言葉で伝えるのもおすすめです。
友人や職場関係の誘いを断るときのマナー
喪中のため、クリスマスパーティーやイベントに参加できない場合もあります。
そのときは、丁寧に気持ちを伝えることが大切です。
断り方の例
「家族が喪中のため、今年のクリスマスは静かに過ごす予定です。」
「ありがとうございます。ただ、喪中なので今回は控えさせていただきます。」
このようにシンプルで丁寧な言葉で伝えれば、相手も納得してくれます。
別の提案をする
パーティーやイベントに参加できない代わりに、「落ち着いた頃にゆっくり会いましょう」と伝えることで、良好な関係を保てます。
喪中のクリスマスに控えること
喪中期間中は、故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら過ごすことが基本です。
派手な飾り付けやパーティー
華やかなクリスマスツリーやイルミネーションは控えめにしましょう。
家族内でシンプルな飾り付けや、静かな食事を楽しむ程度が適切です。
盛大な祝賀イベント
大勢を招いてのクリスマスパーティーや、豪華なディナーなどは避ける方が良いです。
親しい人たちと静かに過ごすことを優先しましょう。
祝い言葉やメッセージ
「メリークリスマス」や「おめでとう」といった祝いの言葉は控え、相手の健康を気遣う言葉や、感謝を伝えるメッセージに変えると良いです。
喪中のクリスマスは、派手な祝い事を避けつつ、控えめに季節の行事を楽しみましょう。
故人への敬意を忘れず、自分や家族にとって心地よい過ごし方を見つけてください。
そもそも喪中、忌中とは?
①喪中
近親者が亡くなった後、故人を偲び、悲しみを共有する期間のことです。
この間は、派手な行事や祝い事を控えるのが日本の一般的な習慣です。
喪中の期間は、一般的に故人の四十九日法要や一周忌を基準に考えられますが、家庭や宗教により異なります。
➁忌中
故人が亡くなった後49日間、いわゆる「忌明け」までの期間を指します。
この間は特に慎んだ生活を心がけることが求められる場合があります。
忌中が終わると喪中に移行するため、忌中の方がより厳格な期間とされています。
喪中にふさわしいクリスマスカードやプレゼント
喪中期間中においても、相手への心遣いとしてクリスマスカードやプレゼントを贈ることはできます。
ただし、喪中という状況を考慮し、控えめな内容やデザインを選ぶことが重要です。
派手すぎる表現や豪華すぎる贈り物は避けつつ、相手への思いやりを伝えることがポイントです。
喪中の立場から送るクリスマスカードの注意点
クリスマスカードを贈る場合、特にデザインやメッセージには気をつける必要があります。
派手なイラストや「メリークリスマス」「ハッピー」といった華やかな表現は避け、控えめで落ち着いたデザインを選びましょう。
落ち着いた色合いのシンプルなカードや、ナチュラルな雰囲気のイラストがおすすめです。
例文
「今年もお世話になりました。良いお年をお迎えください。」
「穏やかな年末年始をお過ごしください。」
こうしたメッセージであれば、相手への気遣いを示しつつ、喪中の立場に配慮した内容になります。
仮に、相手も喪中である場合には、「心穏やかな年末をお過ごしください」といった表現を使うとさらに丁寧です。
プレゼントを選ぶ際の配慮
喪中期間中に贈り物をする場合は、相手に喜ばれることを第一に考えつつ、控えめな選択を心がけましょう。
高価で豪華な品物ではなく、日常的に使える実用的なアイテムが好まれます。
①お茶やコーヒーのセット
温かい飲み物はリラックス効果があり、季節感もあります。落ち着いたパッケージデザインを選ぶと良いでしょう。
➁シンプルなお菓子
クッキーや焼き菓子など、食べやすく特別感の少ないものがおすすめです。
華やかすぎるラッピングは避けてください。
③実用的な生活雑貨
ハンドクリームやアロマキャンドルなど、心を癒すアイテムは喜ばれやすいです。
自然素材やシンプルなデザインのものを選ぶと安心です。
ポイント
贈る際には一言メッセージを添えるのがおすすめです。
たとえば、「ささやかな品ですが、穏やかな時間をお過ごしください」といった表現を加えると、相手への気遣いが伝わります。
喪中でも心温まるクリスマスにするための工夫
喪中でも、家族や大切な人と穏やかで温かい時間を過ごすことはとても大切です。
特別な派手さはなくても、工夫次第で心に残るクリスマスを演出できます。
ここでは、シンプルな飾り付けや落ち着いた楽しみ方を取り入れたクリスマスの過ごし方をご紹介します。
シンプルで心に響く飾り付け
喪中だからといって、家の中を何も飾らないのは少し寂しいですよね。
でも、控えめな飾り付けなら問題ありませんし、気持ちも明るくなります。
ナチュラルなデコレーション
木や松ぼっくり、ドライフラワーなど、自然素材を使った飾り付けがおすすめです。
リースもシンプルなデザインを選ぶと、落ち着いた雰囲気を演出できます。
キャンドルの温かい光
ライトアップではなく、キャンドルを使った装飾は喪中の静けさにぴったり。
ガラスのホルダーに入れたキャンドルは、幻想的でリラックスできる空間を作ります。
クリスマスツリーはミニサイズで控えめに
ツリーを飾りたい場合、ミニツリーを取り入れて、オーナメントは白やゴールドなど落ち着いた色を選ぶと良いでしょう。
シンプルなリボンを巻くだけでも雰囲気が出ます。
落ち着いた雰囲気で楽しむ
お気に入りの料理を家族で作る
クリスマスディナーを豪華にする必要はありません。
子どもと一緒にクッキーを焼いたり、家族みんなでシチューやピザを作る時間そのものが特別な思い出になります。
静かな音楽を楽しむ
派手なクリスマスソングよりも、クラシックやインストゥルメンタルの音楽を選ぶと落ち着いた雰囲気が楽しめます。
家族でゆっくりと聞きながら、リラックスしたひとときを過ごしましょう。
一年を振り返り感謝を伝える時間を作る
家族で一年を振り返りながら、それぞれに感謝の気持ちを伝え合うのも素敵な時間です。
メモ帳に思いを書き出して交換したり、食事の時間に話し合うことで、家族の絆が深まります。
喪中の年末年始で気をつけること
喪中期間中は、クリスマス以外にも年末年始の行事や習慣について気をつけることがあります。
これらの行事は祝い事としての側面が強いため、喪中の考え方に基づいて配慮することが大切です。
ここでは、特に注意が必要なポイントについて解説します。
年賀状ではなく喪中はがきを
喪中期間中において、年賀状を控えることは一般的な習慣です。
故人を偲ぶ期間として新年を祝うことを控えるため、年賀状を出さない代わりに喪中はがきを送ることが推奨されます。
喪中はがきを送る際のポイント
送付時期
11月下旬から12月初旬に届くように手配しましょう。
文面
簡潔に喪中である旨を伝え、新年の挨拶を控えることを記載します。
例文
本年〇月に〇〇(故人名)が永眠いたしました。
つきましては、年末年始のご挨拶を控えさせていただきます。
平素よりご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。
来る年も皆様にとりまして良き年でありますようお祈り申し上げます。
お歳暮やギフトのマナー
喪中期間中でも、お歳暮やギフトを贈ること自体はマナー違反ではありません。ただし、送り方や内容に工夫が必要です。
ギフトを選ぶ際のコツ
・華やかな包装を避ける。
・日常で使いやすい食品や実用品を選ぶ(お茶、洗剤、タオルセットなど)
・弔事用の包装を希望する場合は、購入時にお店に相談しましょう。
注意点
・喪中の挨拶を軽く添えることで、配慮を示します。
・お歳暮の贈答時期は12月上旬から20日頃までが適切です。
贈り物は感謝の気持ちを表すものですが、相手が喪中の場合も考慮し、祝い事として受け取られないよう注意しましょう。
初詣や年始の行事への参加
喪中の間は、新年を祝う行事への参加を控える方が一般的です。
ただし、宗教や地域によって慣習が異なるため、必ずしも禁止されるわけではありません。
控えるべき行事
・初詣や神社・寺での新年のお参り
・新年会や祝い事を兼ねた集まり
ただし、宗教的背景や家族の方針によっては、静かに参拝することが許される場合もあります。
無理に行事を控えるのではなく、自分や家族が納得できる形で行動することが大切です。
Q.クリスマスパーティーに誘われたら行ってもいい?
A.家族や親しい友人同士の静かな集まりであれば、参加しても問題はありません。
参加する場合は、場の雰囲気に合わせて振る舞いを控えめにするのがポイントです。
例えば、目立つ服装や派手な振る舞いを控えたり、短時間の参加にするなどの工夫が考えられます。
また、事前に「喪中なのでお祝いムードを控えめにしたい」と伝えておくと、相手の理解を得やすいでしょう。
Q.子どもとのクリスマスはどうする?
A.喪中期間中でも、子どもの気持ちを汲んで、家族内で静かにお祝いすることは問題ありません。
例えば、家族だけでクリスマスケーキを囲んだり、ささやかなプレゼントを交換するなど、控えめな形で楽しむことができます。
また、喪中の意味を子どもに伝える際には、「大切な人を思い出しながら、静かに過ごす時期」と説明すると理解しやすいでしょう。
Q.クリスマスツリーや飾り付けは控えるべき?
A.一般的には、派手な装飾は避け、控えめな飾り付けにとどめることが望ましいとされています。
しかし、喪中期間中にクリスマスツリーや飾り付けを行うかどうかは、家庭の判断によります。
例えば、小さなツリーを室内に飾る、シンプルなデコレーションにするなどの工夫が考えられます。
外部から見える大掛かりな装飾は、周囲への配慮として控える方が良いでしょう。
Q.プレゼント交換はOK?NG?
A.喪中期間中のプレゼント交換については、基本的に問題ありません。
子どもたちへのプレゼントは、例年通り行ってよいでしょう。
ただし、親戚や友人との大規模なプレゼント交換会などは、控えめにするか、時期をずらすなどの配慮が求められます。
重要なのは、故人を偲ぶ気持ちを持ちながら、家族や周囲への配慮を忘れずに過ごすことです。
無理のない範囲で、心穏やかにクリスマスを迎えられるよう工夫してみてください。
まとめ
この記事は
・喪中のクリスマスをどう過ごすか
・喪中にふさわしいクリスマスカードやプレゼント
・年末年始に気をつけること
を解説してきました。
喪中期間中のクリスマスは、故人を偲びながら静かに過ごすことが一般的ですが、すべての行事を制限する必要はありません。
この記事を参考にして、無理なく安心して過ごせるクリスマスになるように願っています。
お墓・霊園・墓地を探す